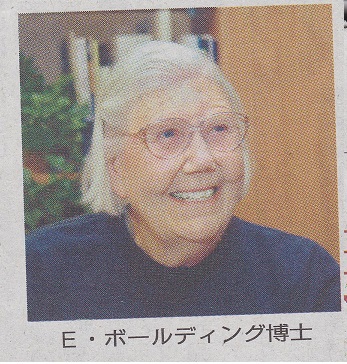〇聖教新聞メモ
2016年
12月29日>家の中に平和を見出す者が最も幸福ーゲーテ
12月28日>苦労した人間には誰人もかなわないー創価学会第2代会長戸田城聖先生
12月26日>イタリアのルイス・グイド・カルリ大学のアントニオ・ラ・スピーナ教授は、コミュニケ゚―ション学の見地から、
池田先生の対話の特長について、「相手との多くの『相違点』に潜む『共通性』をいち早く、的確に見抜く能力の高さ」を挙げる。
ゆえに、先生の対談集は人類普遍の価値を創出し、多様な読者の心をつかんで離さない。
12月26日「選手の成長のため まず自分が変わる」(イタリアSGI ロザリオ・カルビアさん
サッカー監督、高校教師として活躍)幸福は、形ではない。格好ではない。外見や立場、富だけで決まるものではない。
『心』の奥底で何を感じているのか、『生命』の奥に何が生き、何が支配しているかーーそこに実質がある。
12月24日>池田先生が青年部の室長の時に熟慮していたのは、皆の内面に眠っているロマンを
引き出すにはどうすべきか、ということ。目の前の課題だけにとらわれると、人は汲々としてしまう。
しかし、夢を抱けば苦難の意味さえ変わる。 学会活動は義務や作業ではない。自身の人間革命と
世界平和を直結させる最極のロマンである。
12月23日>言葉は人々を接近させるートルストイ
12月23日>一冊の良書が心を育み平和をつくる。
12月21日>いかなる国の人びととも、慢心にも卑屈にもならず、一個の「人間」として、
堂々と誠実に交流できる「実力」と人類に貢献しゆく「開かれた心」を持つことだ。
そのためには、「世界を知る」ことが欠かせない。知らないことが、偏見や先入観を生む。
学ぶ勇気が、自分の心を世界に向かって開くことになる。ー池田先生
12月20日>学習指導要領が10年ぶりの改訂、世界化に対応と。「開かれた心」の育成が要。
12月19日>才能を育むには思いやりが必要ードストエフスキー
12月18日「教育 Education」学校現場で注目を集める「アクティブ・ラーニング」って何?
○一人も見捨てない学習 ・・ごく普通の課題を与え、その課題の達成に向けて、「一人も見捨てずに
全員が達成する」ことを子どもたちに求める学習法です。児童・生徒の中で「分かる人」が「分からない人」に
教えるのです。
○勉強を通じてできる仲間 ・・ただ、『学び合い』のアクティブ・ラーニングの良さは、学習面の成果だけでは
ありません。人と人とのつながりを強くすることができる点も大きな魅力です。
○”つながり”が大きな力に どんなに技術が進歩しても、実際に人とのつながれること、仲間を持つこと自体が
大きな力になります。”つながれる人が強い”のです。
12月18日「恩を知り」「恩に報いる」のが仏法の道。
12月18日>指導とは「一緒にやろう」と勧めることー創価学会第2代会長戸田城聖先生
12月17日<わが友に贈る>「道理証文よりも現証にはすぎず」体験が真の納得を生む。
信仰の醍醐味を自分らしく語り抜こう!
12月17日>立派な友人の励ましほど苦しみを癒す薬はないーギリシャ詩人
12月14日>誓願とは即「行動」、即「真剣勝負」なり。
12月14日>一歩一歩の前進を大切にせよー創価学会第2代会長戸田城聖先生
12月13日>大隅良典氏・・今年のノーベル医学・生理学賞。・・「素朴な疑問を持ち続けることが大事」・・
疑問を持ち、問い続ける中で思想は深まるものだ。戸田城聖先生は、疑問会で発言する人を大切にした。皆の思いを
代弁する質問や、深い法理を語る契機になる疑問が出ると「よく聞いてくれた。ありがとう!」と称賛を惜しまなかった。
心を働かせなければ、問いを発することはできない。・・時に、答えより大事な問いもある。常に「何のため」を
問い続けたい。
12月10日>誠実でも行動しなければ何もならないー創価学会第2代会長戸田城聖先生
12月10日>人は広い人間関係の中で真の自己を見つけ出すータゴール
12月09日>行動とは創造することーブーバー
12月02日「『文は人なり』と言われますが、それは、『文は生命』であり、『文は魂』であり、また、
『文は境涯』であるということです。文には、生命がすべて投影されます。したがって、苦労して、苦労して、苦労し抜いて、
ほとばしる情熱で、炎のように燃え上がる生命でつづった文は、人びとの心を打つんです」(『新・人間革命』第14巻「使命」の章)
12月01日>必要とする一切は君自身の中にーヘッセ
11月30日<わが友に贈る>自ら挑戦する意欲を引き出してこそ真の「励まし」だ。
共に祈り 共に働き 苦楽の坂を超えゆこう。
11月30日>仏教を評価したドイツの哲学者ショーペンハウアーは、「知は力なり」との格言を「とんでもない」といった。
「きわめて多くの知識を身につけても、少しも力をもっていない人もあるし、逆に、なけなしの知識しかなくても、
最高の威力を揮う人もある」と。
11月28日「青春時代の本当の失敗とは、失敗を恐れて挑戦しないことである」
11月26日>最高の価値を創造し最大の幸福を獲得せよー牧口先生
11月26日>成功の度合いは乗り越えてきた障害で計るべきーアメリカの作家
11月26日<読書>サピエンス全史(ユヴァル・ノア・ハラリ著)
ー虚構信じ協力する人類の強さーホモ・サピエンスだけが生き残ったのは、何故か。・・
著者が歴史の決定的転換点と捉えたのは、今から数万年前に人類の脳内で起きた「認知革命」だ。
これは虚構について信じ、伝達する能力を得たという革命で、これによって神話や宗教などが生まれ、
我々は無数の他者と協力できる唯一の種となった。それが人類を地球の覇者たらしめた最大の原動力、と
いうのが著者の見立てだ。
11月26日<真実を知るそれが自分を変え世界を変える>「第14回開高健ノンフィクション賞を受賞 工藤律子さん」
ー若者ギャングのように、貧困や治安の悪化などの環境に影響され、本来の自分を失ってしまうことを、同書では、
アイデンティティーの喪失を呼んでいる。・・真のアイデンティティーを得るために必要なのは、この世界には”まがいものの
存在意義”より、もっと価値あるものがあると知ることです。多様な価値に目を向け、受け入れることが、喪失した
アイデンティティーを取り戻すための第一歩になる。・・
11月25日「言葉は魂に依拠している」ペトラルカ
11月24日<わが友に贈る>”できない”ではなく”どうすればできるのか”工夫と努力を重ねよう!
自身の弱い心に勝てば活路は必ず開ける!
11月20日「池田先生 四季の励まし」<世界へ!人間のための宗教を>創価学会の使命は、世界広宣流布にある。
日蓮大聖人の仏法を、人々の胸中に打ち立て、崩れざる世界の平和と、万人の幸福を実現することにある。大聖人は、
末法にあって全人類の救済のために妙法流布の戦いを起こされ、全世界への大法弘通を誓願された。
学会は、御本仏のその大誓願を果たすために出現した、人間主義の世界宗教である。
☆「人間のための宗教」こそ仏法の帰結だ。それゆえ、反対に「宗教のための人間」「宗教のための宗教」というような
転倒した権威主義とは、どこまでも戦わざるを得ない。希望へ、幸福へ、安穏へ、平和へと、大悪を常に大善の方向へ転じていくのが、
現実変革の宗教の証しである。
☆目の前の一人を、親身になって蘇生させていく。一人の宿命転換の劇に、最高の善知識として関わっていく。
「一人」を励まし育てることが、世界の広宣流布を築く一歩だ。否、世界広布といっても、「一人」が幸福になるかどうかで
決まる。
☆創価学会には、いかなる大難も私と共に勝ち越えてきた、勇気と誠実と忍耐の英雄が無数にいる。「仏法は勝負」である。
ゆえに、戦い勝たねばならない。戦うことが「後継」だ。勝つことが「報恩」である。
11月18日>創価学会の創立記念日である「11・18」は、初代会長・牧口常三郎先生が殉教された日(昭和19年)でもある。
・・人間教育の「校舎なき総合大学」とも称される。この”信心の母校”に卒業はない。師匠と出会い、どこまでも自身を
磨き抜いていく中で、最高に充実した日々を送ることができる。
11月12日「アメリカ心理学の父」と呼ばれたウィリアム・ジェームズは、「なにかの美点を身につけたいときは、
すでにそなわっているかのように行動すればよい」と言ったが、まさに至言。自己を変革するには、まず行動することだ。
11月08日>力を合わせるには極めて強力な動機が必要ーアラン
11月07日「今学期はどんな内容をカバーする(扱う)のですか」。学生の質問に教授が答えた。「重要なのは
君が何をディスカバー(発見)するかだ」。言語学者チョムスキー氏が、教育の理想として紹介した話である。
求められる教育は、知識の蓄積ではなく「他の人たちと協力して独自の創造的な仕事をすること」だと氏は
強調する。思索は他者と分かち合うことで価値を生む。<<名字の言>>
11月04日>目的は終点ではなく今を変えていく過程ーデューイ
10月31日>ナラヤンは、高校時代に国民革命の理想に燃え、非暴力・不服従運動に参加する。やがてアメリカに渡り、
そこで、マルクスの革命思想に傾斜していく。急進的な社会改革に心を動かされ、ガンジーの非暴力の闘争を否定し、
武力革命を肯定した時代もあった。
しかし、ガンジーの高弟・ビノバ・バーべに触発され、再び非暴力革命の道をめざすようになる。紆余曲折を経て、
ガンジーの懐に帰ってきたのだ。”良心”の大地ともいうべきガンジーの思想は、ナラヤンの”良心”の樹木を蘇生
させていったのである。
ガンジー亡きあと、彼は、師の思想を受け継ぎ、すべての階層の人びとの向上をめざす「サルボダヤ運動」を展開していった。
どんなに豊かそうに見えても、その陰で虐げられ、飢え、苦しむ人のいる社会の繁栄は虚構にすぎない。皆が等しく幸せを
享受してこそ、本当の繁栄といえよう。
(新・人間革命 源流)
10月29日『脳はあきらめない!』(瀧靖之)ほんの10年ほど前まで、人間の脳はいったん形成される、その生活形態が
変化することはないと思われていた。現在、脳は何歳になっても機能を高められることが分かっている。記憶をコントロール
する「海馬」は、脳の中で唯一、新しい細胞が生まれ、大きくできる領域だ。知的好奇心、多趣味、語学、睡眠などは、脳の
健康によい一方、生活習慣病、肥満、ストレスは脳を委縮させる・・
10月27日(わが友に贈る)目標が曖昧では環境に流されてしまう。「きょう何をすべきか」
明確な人が道を開く。
10月26日<かがやく老年ライフの知恵袋 シニア社会学会 会長 袖井孝子 (最適の老化防止は?)
人と共に声を出して動く>スポーツ庁の調査によると「健康のは若いころのスポーツ経験よりも、
シニアになった今、運動をしていることが大切」
10月22日<日常の何でもないことの価値を見つける生き方 映画「この世界の片隅に」
監督・脚本 片淵須直さん>「もともと、自分はなぜ、そのような夢や望みをいだいたのか。その時の気持ちを
いとおしんでほしい。自分をあきらめないことーーそれが未来を照らす光になるはずです」
10月21日>「人材」とは「人財」ー皆に桜梅桃李の長所が。
10月21日>よそへ移っても己からは逃げられぬーヘミングウェイ
10月19日>「すべての人を尊重せよ。しかし子供の場合は普通の百倍も尊重し、その汚れを知らぬ魂の純粋さを損なわぬよう
努めよ」とは、ロシアの文豪トルストイの箴言である。(新・人間革命 源流)
10月18日>友の存在が障害を恵みに変えたーヘレン・ケラー
10月13日>敷地内の一角に、「七つの罪」と題したガンジーの戒めが、英語とヒンディー語で刻まれた碑があった。
ーー「理念なき政治」「労働なき富」「良心なき娯楽」「人格なき知識」「道徳なき商業」「人間性なき科学」「献身なき祈り」
(新・人間革命 源流)
10月06日『社説 有意義な「学びの秋」に』「切実に言葉を欲しがる時」に、「活字は大きなヒントを与えてくれる」と。
渇仰ーーそれは人生に誠実たろうとする者にこそ生じる。
10月03日「宗教とはーー万人に理解できる哲学である」トルストイ
10月03日「道理と申すは主に勝つ物なり」
10月01日(「コンビニ人間」で芥川賞受賞 作家 村田紗耶香)普通の人間の恐ろしさ。それは「無邪気に誰かを
裁いている」のに気付かないことを指している。
10月01日>インドのメンバーとの語らいを通して山元伸一が感じたことは、多くの人が宿命の転換を願って信心を
始めたということであった。インドでは、業(カルマ)という考え方が定着している。・・・
信心よって「あきらめ」の人生から「挑戦」の人生へーインドのメンバー一人ひとりが、それを実感し、歓喜に
燃えていたのだ。(新・人間革命 源流)
10月01日(わが友に贈る)正しい信仰は人間を強くする。挑戦し続けるための無限の希望の力となる。
9月30日(わが友に贈る)「使命」とは与えられるのではなく自ら選び取るものだ。
9月27日>『バガバット・ギーター』(神の歌)の冒頭部分には、「幸福は、心の平和と喜びを得ることにある。
それは、自分のなすことに充実感をもつことから生まれる」とある。(新・人間革命 源流)
9月26日>デサイ首相は言う。「拘留中、私は内省的に生きた。いかにしてえ自身を向上させうるか。そのことを常に自らに
問いかけていた。自分の欠点とは何か?心は穏やかか?誰かに嫌悪感をいだいていないか?・・と」使命に生き、自分の向上を
めざす人にとっては、逆境の時こそが、実り多き学習の場となり、自分を磨く最高の道場となる。(新・人間革命 源流)
9月24日>楽観主義と、努力や準備を怠り、”どうにかなるだろう”という生き方とは全く異なる。楽観主義とは、万全の手を
尽くすことから生じる、成功、勝利への揺るがざる確信と、自らを信じる力に裏打ちされている。(新・人間革命 源流)
9月21日>僅かな時間でも有益な事に使える。ーヒルティ
9月17日<子育てアドバイス どうする子どもの困った言動 色彩心理研究家 末永蒼生>相談 好きなことばかりさせていると、
わがままな子になるのではと心配です。
回答 ・・実はこれは逆なのです。好きなことをやった体験が豊富な子どもほど、つらい時でも我慢できる子になります。・・
我慢ばかりだと、生活に喜びを持てず、自暴自棄になりがち。好きなことを存分にやっり、生きる楽しさを実感した子ほど、
自分のことを大切にできるようになります。そして、自分だけでなく、他人のことも大切に思えるようになるのでしょう。
9月16日>科学技術の進歩や富を手に入れることが、必ずしも心の豊かさにつながるとは限らない。モノの豊かさや便利さ、
快適さを手にしたことによって、むしろ、日本は心を貧しくしてきたといっても過言ではない。 科学技術や経済の発展につれて、
家族愛や友情、人への思いやりは増してきたであろうか。歓喜や感情の思い、満足感、充実感が心を満たしているだろうか。
道行く人に、どれほど笑顔はあるだろうか。 人間の幸せは、豊かな精神の土壌に開化する。心を耕してこそ、幸の花園は広がる。
(新・人間革命 源流)
9月16日>探求なき人生は生きがいなしーソクラテス
9月15日>正しく行動するなら不当な非難など恐れるなーヒルティ
9月14日>「共に」「心を通わせて」時代を変革 池田SGI会長は、「人を動かすのは、役職や肩書や恰好ではない。『真心』
『大確信』『大誠実』ー それが人を動かすのだ。心が心を動かすのである」と語っている。
9月13日>純真な心で信心すれば折伏できるー恩師
9月10日「あなたが何ををしていても、あるいはあなたになんの罪もなくても、生きてれば多くのことが降りかかってくるわ・・・。
だけど、それらの出来事をどういう形で人生の一部に加えるかは、あなたが自分で決めること」(サラ・パレツキ―著『サマータイム・ブルース』)
9月10日>「情熱」を表わす英語の「パッション」には「受難」の意味もある。・・脳科学者の茂木健一郎氏は「情熱とは苦労することから
生まれる」と記した(「何のために『学ぶ』のか」)
9月10日>後輩を育てるという心がなければ団結もなくなるー恩師
9月10日>熱意を失った人ほど年老いて見えるーソロー
9月09日>両親と共に創価学会に入会し、今年の秋で60周年を迎えるS.Nさん(67)=
「つらい時も、苦しい時も、御本尊を信じ、唱題と学会活動に徹し抜いた結果、不思議と良き方向へ、良き方向へ
と人生が開けてきた。まさに『必ずさかう』との御請訓道りです」。
9月09日>青年は「創る者」であらねばならぬ。ーニーチェ
9月08日「仏教をならはん者父母・師匠・国恩をわするべしや、此の大恩をほうぜんには必ず仏法をならいひわめ
智者とならで叶うべきや」[通解]仏教を学ぶ人は、父母、師匠、国家社会の恩を忘れてはならない。この大恩に
報いるには、必ず仏法の奥底を学び行じて、智者とならなければならない。(報恩抄」、P293)
9月06日>幸福とは自らが望み作り上げていくものーアラン 9月06日>池田SGI会長は「価値ある人生の極致は人間の信頼に応え報いようと、いかなる苦難にも屈せず走破していく果てに達するもの」と。 9月05日<人生を再び輝かせた妙法の力>(アメリカSGI 辻守哉さん ロックフェラー大学教授) ☆妻に導かれ、信仰の道へ☆”学会2世”だった由紀子さんは、創価女子短期大学を卒業後、渡米。歌を教えるかたわら、両親の知り合い が経営するニューヨークの店で働いていた。彼女とは18歳の年齢差だったが、出会った時に人生を共にするように感じた。 「題目を唱えると、アイデアが、どんどん浮かんでくる。私にとって唱題は、研究のエネルギーであり、 ”知恵の泉”であると実感する日々です」 ☆酒とケンカの荒んだ生活☆20代から30代にかけて、順調な研究生活を送り、39 歳で大学終身在職権(テニア)を取得・・40代半ばでに2度の離婚を経験。空しさや寂しさが心を覆い、研究活動への情熱も次第 に薄れていく。「当時、健康状態がいつも不安定でした。もともと(酒を)飲むのが好きだったこともあり、毎晩、ひたすら飲んで いました。」そんな荒んだ生活だった2006年、あるレストランで一人の女性に出会う。のちに妻となる由紀子さんだった。 ☆人類に役立つ開発めざす☆12年、辻さんは、ノーベル賞学者を多数輩出している名門ロックフェラー大学のアーロン・ダイアモンド ・エイズ研究所教授に就任。これまで、マラリヤやエイズなどへのワクチンの開発で、三つの目覚ましい実績を上げ続けた。 「共同研究中心の時代にチームワークは不可欠。人類に役立つ研究・開発を進めるためにも、自身が人間革命し続けるしかないと 肝に銘じています」 「SGIに入会して、人生が大きく変わりました。酒に逃げていた昔と違い、どんな困難にも負けない自分になりました。そうした ネバー・ギブアップの精神が人生の勝利をつかむ、と確信してやみません」 9月01日>多くの歴史小説を著す中津文彦氏によれば、興隆・滅亡には”方程式”があるという。滅亡に至る共通項は「準備不足」 「孤立」「奇策」の三つ。一方、興隆の共通項も三つあり、最初の二つが「周到な準備」と「連携」。滅亡の方程式とは反対の事柄 だ。しかし氏は、最後の3点目に、全く同じ「奇策」を挙げる。どういうことか。準備不足で。孤立した者が策に走ると滅亡を招く が、準備を重ね、強い連携を築いた上で、定石を破った大胆な策に打って出るときには、大いなる飛躍が期待できる、ということだ。 8月29日<師と共に歩む使命の道 世界に”文化の懸け橋”を>(純真学園大学 放射線化学科教授 具然和=グヨンファさん) 08年、リーマン・ショックを機に、一瞬で貯金が底を尽いた。「この時、私は、財産や名誉よりも、他者を思いやり、 行動する学会活動こそが、真の幸せをもたらす源泉だと実感したのです。」 8月29日>自己の完成には他者との交流が必要ートルストイ 8月28日<教育 子どもを伸ばす親の心構え>「上から目線」に注意し 「親子は対等」の意識で フロイト、ユングと並び「心理学の三大巨頭」とされる、オーストリアの精神医学者・アドラーは、 ”全ての人間関係は対等と見るべき”と考えていました。人間関係のトラブルは、相手の問題に土足で踏み込むような 行動をする時に置きます。 8月27日>苦しんだ分だけ、人を幸せにできるー瓦葺き職人 T・Iさん 8月27日<求道の欧州教学研修会から・・わが人間革命から平和の建設を>ドイツ ニコラス・ライアンさん 研修・・で・・学んだのは、自身の人間革命を通じて環境を変えていくことが、世界平和への確実な道であると いうことです。人間革命こそが、日蓮仏法の核心であり、世界を変革しゆくカギであると思います。 8月27日>行動のないところに幸福は生まれないーディズレーリ英宰相 8月26日>個人を磨き深化させる創価の思想が歴史を動かすーハーバード博士 8月23日>みんなで学ぶ教学(30)「衆生所遊楽」現実社会の苦悩を避けるのではなく”成長の舞台”へ変えていける のがこの仏法です。・・戸田2代会長は、この言葉を引用して「御本尊を信じきった時に、生きていること自体が楽しい。 何をやっても楽しいという人生になるのである」と語っています。 8月22日>大歴史学者のトインビー博士は、毎朝9時ごろには、気分が乗っていようがいまいが、机に向かった。 「仕事をしたい気持ちになるのを待っていたのでは、いつまでも仕事はできない」 8月20日>現在の一念が「因」となり、未来の「果」をいくらでも変えていける、と仏法では説く。栄光の未来を自在に思い描き、 人生という舞台を演じ切るのは、ほかでもない自分自身である。 8月19日>戦争や暴力は「正義」と「正義」の衝突から起こる。正義を叫んでも、寛容の心が伴わなければ、人間は野蛮へと 落ちてしまう。そういう例を、私たちは嫌というほど見せられてきた。衝突と分断が覆う世界にあって、必要なのは「思いやり のある正義」であろう。つまり「相手の立場になって考える」精神だ。その想像力と勇気を鍛えるのが宗教であり、教育である。 ここに創価の信念もある。 8月18日<新・人間革命>宗教を比較、検証するうえで求められる尺度とは何であろうか。平易に表現すれば、「人間を強くするのか、 弱くするのか」「善くするのか、悪くするのか」「賢くするのか、愚かにするのか」に要約されよう。 8月18日>自分の魂をより良く変えることに努めよートルストイ 8月17日アインシュタインは、戦争の根本原因が「人間の心」にあると考えていた。フロイトに問うた。 「人間の心を特定の方向に導き、憎悪と破壊という心の病に冒されないようにすることはできるのか」 フロイトは、人間から攻撃的性質を取り除くことはできないとしつつ、それでも、「文化」の力によって、 人間の心を平和の方向へ変化させ、戦争の終焉へ歩み出すことは可能だ、とつづっている。 8月15日>一輪の花が咲いている。それを”何だ、スミレの花か”と認識した時点で、目の前の花は「スミレ」という ”言葉”に置き換わる。だが、”言葉の邪魔”を拝して見続ければ、花はその花ならではの美しさを明かしてくれる。 小林秀雄の有名な評論だ。・・・小林自身は「僕は無智だから反省なぞしない。悧巧な奴はたんと反省してみるがいい」と、 戦中に戦争を美化した反省を拒み、返す刀で、時流に合わせて戦争批判に転じた戦後知識人を冷笑した。 小林の態度の是非はさておき、聞こえのいい言葉を聞き、世の空気を読むだけでは「真実」が見えないのは、 いつの時代も同じだ。 8月15日<新・人間革命>1979年当時、世界は東西冷戦の暗雲に覆われていた。そしてその雲の下には、大国の圧力に よって封じ込められてじゃいたが、民族、宗教の対立の火種があった。東西の対立は終わらせなければならない。だが、 そのあとに、民族・宗教間の対立が一挙に火を噴き、人類の前途に立ちふさがる、平和への新たな難問となりかねないことを、 山本伸一は憂慮していた。 その解決のためには、民族・宗教・文明間に、国家・政治レベルだけでなく、幾重にも対話の橋を架けることだと、 彼は思った。 8月13日<アイデアを出す瞬発力が武器 ”自分のものさし”信じて風を起こす> (ウェブ小説で若者から人気 作家 岡田伸一さん) 8月13日>真似をする必要はない。自分自身の道を見つけよー哲人ソロー 8月11日「もがき、努力したすべての経験をいわば土壌として、そこからある瞬間、生み出されるものが直観なのだ」 ー羽生善治棋士 8月09日<新・人間革命>仏法は、「随方毘尼」という考え方に立っている。仏法の本義に違わない限り、各地域の文化、風俗、習慣や、時代の風習に 随うべきだというものである。それは、社会、時代の違い、変化に対応することの大切さを示すだけでなく、文化などの差異を、むしろ積極的に尊重していく ことを教えているといえよう。この「随方毘尼」という私座の欠落が、原理主義、教条主義といってよい。自分たちの宗教の教えをはじめ、文化、風俗、習慣 などを、ことごとく「絶対善」であるとし、多様性や変化を受け入れようとしない在り方である。それは、結局、自分たちとことなるものを、一方的に「悪」 と断じて、差別、排斥していくことになる。 8月08日<新・人間革命>文豪トルストイが述べた”人間が宗教なしでは生きられない理由”を弟子のピューリコフは、 6つにまとめた。その一つ「宗教なしでは人間は自分のしていることが善いか悪いかを知ることが決して できないからである。」 8月06日<好奇心が才能を開花させる(柏井正樹さん テニスコーチ 錦石圭選手を指導した)> 人間が才能を開き、成長していくには、好奇心が重要です。コートでは、好奇心を満たす挑戦が日常的に 繰り返されました。圭を育成した秘訣をよく質問されますが、”勝手に育っちゃった”と答えています。 あえて言えば、圭の成長を邪魔しなかったということですかね(笑い)。 8月06日>他人と比較し、ものを考える習慣は致命的ーラッセル 8月04日>個人の変革に力を置くSGIの思想に深く共感ーアメリカ 博士 8月01日(「暮らしの手帖」編集長 花森安治)「難解でもないことを難解にいうのはバカな学者がやることだ。難解なことを わかりやすく表現し、正確につたえる、それが編集者のしごとだ」企画案も、「上からひとを見下すよううな」「説教でもたれようか とする」内容が出ると、叱り飛ばして却下した。 8月01日(新・人間革命)生命の内奥から込み上げてくる人間の感情や欲望は、道徳や規律、また制裁の強化など、制度の改革を もってしても、根本的に抑制することはできない。心の変革こそが、個人の幸福を実現していくうえでも、世界の平和を築いていく うえでも、最重要のテーマとなる。「心の練磨に基礎をおかない限り、知性の開拓が人間を尊貴にすることはできない」とはスイス の大教育者ペスタロッチの箴言である。 7月31日「大空へ羽ばたけ!可能性の翼を広げて 未来本部X教育本部 希望座談会」「安心」を生む第一歩は「聞く」こと I 私ごとで恐縮ですが、実は長女が小学6年の夏から、不登校になったことがあったんです。最初は焦るばかりで娘の”声”に耳を 傾ける心の余裕もありませんでした。「もっと私と向き合って」というメッセージを発していたはずなのに。 K 子どもは自分の思っていることを、うまく言葉にできません。でもその行動には全て”意味”があります。 「問題行動」ではなく「問題提起行動」なんです。 I 私も、池田先生のご指導を学ぶ中で気付いたんです。「変わらなければならないのは娘ではない。自分だ」と。すると祈りも、 「不登校を何とかしたい」から「わが子に使命の人生を歩んでほしい」という祈りへと変わっていきました。そして不登校に なってから5年の夏ーーさまざまな物をため込み、あふれかえった娘の部屋の大掃除を、私と娘の二人でやったんです。2週間かけて。 7月29日>救うべきは「人間の心」「一人の尊厳」に目覚めよ(ペレストロイカの設計者 ロシア ヤコブレフ博士) 「人間は戦争をやめず、犯罪をやめず、自然を破壊し続けています。真に誠実な人間ならば、一番の課題は『人間の心を救う』ことだと、 分かるはずです。今、池田会長が、これを進めておられる」「『国』と『政府』が、『社会』と『人間』の上に立っている。 私たちは、このピラミットを逆転しなくてはなりません」SGI会長が鋭く応じた。「その通りです。その逆転作業に、私どもは挑戦して いるのです。だから古い体制からは、絶え間ない攻撃を受けてきました」 7月29日「長編を読め。世界的な小説を嫁」恩師 7月29日>宇宙の台本にはそれぞれの演ずべき役割がーロラン 7月28日>君の胸からでたものが人の胸を引きつけるーゲーテ 7月25日>真に偉大な事業は目立たぬ所で達成されるーセネカ 7月21日>教師とは子どもの可能性を信じ抜く人(「臨床心理士」「学校心理士」の校長 自閉症、注意欠陥 ・多動性障害(ADHD),小児うつ・・。そうした子どもたちに、限りない慈愛を注ぐ T.Oさん) 「教師とは子どもの心に希望の炎をつける人です。子どもの可能性を信じ抜く人です。人間の心を動かすのは、 人間の心だけなのです」・・今、学校目標を「生き方を深め、すてきな大人に育つ」と決め、学校運営に力を 注いでいる。臨床心理士として授業を参観するのが日課だ。「子どもを救っていけるのは、教師である私自身 !」-その信念で寄り添い続ける。 7月17日>皆に笑顔を届けんでー!(舞台役者 魚谷尚代さん) 勝つと決めて広布に走れば、必ず諸天は動く。役者って、舞台に上がったら”丸裸”になるから、”自分磨き”を サボると、一瞬でお客さんに見抜かれる。だからやっぱ、折伏は大事。自分の弱点に気付かせてくれるんやから。 私も臆病で諦めやすい性格やったけど、かなり折伏で鍛えてもらった。友人の幸せを真っすぐ素直に祈り抜けた 時、相手も素直な心で受け止めてくれる。相手は自分の鏡。舞台も同じやわ。 7月16日>成功とは結果で判断せず努力の総計で計るべきー発明王エジソン 7月14日>地震3ヵ月 熊本の地から <他者思いやる心の芽生えが | ”地域の力”で生きることこそ>日本近代史家 渡辺 京二 「過去から近現代を映す」文明を見直す上で有効なことは、過去という鏡から近現代を映し出してみることです。 過去や歴史は、私たちが現在当たり前だと考えていることがかならずしも当たり前ではない、そんな驚きを 与えてくれます。・・江戸期に来日した欧米人が当時、魅了された日本の豊かさに触れていますが、近代化以前の 日本はどのように映し出されていたのでしょうか。・・現代社会ほど、経済が人々の中心部分を占めたことは なかったように私は感じています。 「謙虚に命を受け止めて」私は思想に生きてきた人間です。その思想のために 親しい友と決別することもありました。しかし、思想なんて大したことではなかった。大事なのは人間。 人間としてどう生きるかということです。地震の前から少しずつ考えてきたことでしたが、今回の地震は、 その思いを一層強くしました。 7月13日>明日を求めて SGI会長の対談録Ⅱ 第24回「平和の文化の母」 エーリス・ボールディング博士 「平和」は、単に「戦争がない」状態をいうのではない。平和とは「文化」である。つまり、民衆一人一人の生き方に 根ざし、家庭や地域といった生活の現場から創造していくものである。お互いの差異を認め合い、相手の主張に耳を 傾けて、絶えず争いを統御(コントロール)していく営みのことである。・・・・ 「私は、『個々の人間の行動から出発して平和の波を起こしていく』というSGIの信念に賛同します。 私はかねてから『共同体を構成する一人一人の成長に全力を傾注していく以外に、平和で健全な地球の 未来は見えてこない』と考えてきたからです」そして、過去にはガンジーやM・L・キングなど、社会を 動かしたカリスマ的指導者がいたが、真に重要なのは「それが社会的な運動であり、民衆の運動であったという こと」「民衆の一人一人が、今後の世界がどうなるかについての、新たな認識と自覚を育んだということ」 だと論じた。
9月06日>幸福とは自らが望み作り上げていくものーアラン 9月06日>池田SGI会長は「価値ある人生の極致は人間の信頼に応え報いようと、いかなる苦難にも屈せず走破していく果てに達するもの」と。 9月05日<人生を再び輝かせた妙法の力>(アメリカSGI 辻守哉さん ロックフェラー大学教授) ☆妻に導かれ、信仰の道へ☆”学会2世”だった由紀子さんは、創価女子短期大学を卒業後、渡米。歌を教えるかたわら、両親の知り合い が経営するニューヨークの店で働いていた。彼女とは18歳の年齢差だったが、出会った時に人生を共にするように感じた。 「題目を唱えると、アイデアが、どんどん浮かんでくる。私にとって唱題は、研究のエネルギーであり、 ”知恵の泉”であると実感する日々です」 ☆酒とケンカの荒んだ生活☆20代から30代にかけて、順調な研究生活を送り、39 歳で大学終身在職権(テニア)を取得・・40代半ばでに2度の離婚を経験。空しさや寂しさが心を覆い、研究活動への情熱も次第 に薄れていく。「当時、健康状態がいつも不安定でした。もともと(酒を)飲むのが好きだったこともあり、毎晩、ひたすら飲んで いました。」そんな荒んだ生活だった2006年、あるレストランで一人の女性に出会う。のちに妻となる由紀子さんだった。 ☆人類に役立つ開発めざす☆12年、辻さんは、ノーベル賞学者を多数輩出している名門ロックフェラー大学のアーロン・ダイアモンド ・エイズ研究所教授に就任。これまで、マラリヤやエイズなどへのワクチンの開発で、三つの目覚ましい実績を上げ続けた。 「共同研究中心の時代にチームワークは不可欠。人類に役立つ研究・開発を進めるためにも、自身が人間革命し続けるしかないと 肝に銘じています」 「SGIに入会して、人生が大きく変わりました。酒に逃げていた昔と違い、どんな困難にも負けない自分になりました。そうした ネバー・ギブアップの精神が人生の勝利をつかむ、と確信してやみません」 9月01日>多くの歴史小説を著す中津文彦氏によれば、興隆・滅亡には”方程式”があるという。滅亡に至る共通項は「準備不足」 「孤立」「奇策」の三つ。一方、興隆の共通項も三つあり、最初の二つが「周到な準備」と「連携」。滅亡の方程式とは反対の事柄 だ。しかし氏は、最後の3点目に、全く同じ「奇策」を挙げる。どういうことか。準備不足で。孤立した者が策に走ると滅亡を招く が、準備を重ね、強い連携を築いた上で、定石を破った大胆な策に打って出るときには、大いなる飛躍が期待できる、ということだ。 8月29日<師と共に歩む使命の道 世界に”文化の懸け橋”を>(純真学園大学 放射線化学科教授 具然和=グヨンファさん) 08年、リーマン・ショックを機に、一瞬で貯金が底を尽いた。「この時、私は、財産や名誉よりも、他者を思いやり、 行動する学会活動こそが、真の幸せをもたらす源泉だと実感したのです。」 8月29日>自己の完成には他者との交流が必要ートルストイ 8月28日<教育 子どもを伸ばす親の心構え>「上から目線」に注意し 「親子は対等」の意識で フロイト、ユングと並び「心理学の三大巨頭」とされる、オーストリアの精神医学者・アドラーは、 ”全ての人間関係は対等と見るべき”と考えていました。人間関係のトラブルは、相手の問題に土足で踏み込むような 行動をする時に置きます。 8月27日>苦しんだ分だけ、人を幸せにできるー瓦葺き職人 T・Iさん 8月27日<求道の欧州教学研修会から・・わが人間革命から平和の建設を>ドイツ ニコラス・ライアンさん 研修・・で・・学んだのは、自身の人間革命を通じて環境を変えていくことが、世界平和への確実な道であると いうことです。人間革命こそが、日蓮仏法の核心であり、世界を変革しゆくカギであると思います。 8月27日>行動のないところに幸福は生まれないーディズレーリ英宰相 8月26日>個人を磨き深化させる創価の思想が歴史を動かすーハーバード博士 8月23日>みんなで学ぶ教学(30)「衆生所遊楽」現実社会の苦悩を避けるのではなく”成長の舞台”へ変えていける のがこの仏法です。・・戸田2代会長は、この言葉を引用して「御本尊を信じきった時に、生きていること自体が楽しい。 何をやっても楽しいという人生になるのである」と語っています。 8月22日>大歴史学者のトインビー博士は、毎朝9時ごろには、気分が乗っていようがいまいが、机に向かった。 「仕事をしたい気持ちになるのを待っていたのでは、いつまでも仕事はできない」 8月20日>現在の一念が「因」となり、未来の「果」をいくらでも変えていける、と仏法では説く。栄光の未来を自在に思い描き、 人生という舞台を演じ切るのは、ほかでもない自分自身である。 8月19日>戦争や暴力は「正義」と「正義」の衝突から起こる。正義を叫んでも、寛容の心が伴わなければ、人間は野蛮へと 落ちてしまう。そういう例を、私たちは嫌というほど見せられてきた。衝突と分断が覆う世界にあって、必要なのは「思いやり のある正義」であろう。つまり「相手の立場になって考える」精神だ。その想像力と勇気を鍛えるのが宗教であり、教育である。 ここに創価の信念もある。 8月18日<新・人間革命>宗教を比較、検証するうえで求められる尺度とは何であろうか。平易に表現すれば、「人間を強くするのか、 弱くするのか」「善くするのか、悪くするのか」「賢くするのか、愚かにするのか」に要約されよう。 8月18日>自分の魂をより良く変えることに努めよートルストイ 8月17日アインシュタインは、戦争の根本原因が「人間の心」にあると考えていた。フロイトに問うた。 「人間の心を特定の方向に導き、憎悪と破壊という心の病に冒されないようにすることはできるのか」 フロイトは、人間から攻撃的性質を取り除くことはできないとしつつ、それでも、「文化」の力によって、 人間の心を平和の方向へ変化させ、戦争の終焉へ歩み出すことは可能だ、とつづっている。 8月15日>一輪の花が咲いている。それを”何だ、スミレの花か”と認識した時点で、目の前の花は「スミレ」という ”言葉”に置き換わる。だが、”言葉の邪魔”を拝して見続ければ、花はその花ならではの美しさを明かしてくれる。 小林秀雄の有名な評論だ。・・・小林自身は「僕は無智だから反省なぞしない。悧巧な奴はたんと反省してみるがいい」と、 戦中に戦争を美化した反省を拒み、返す刀で、時流に合わせて戦争批判に転じた戦後知識人を冷笑した。 小林の態度の是非はさておき、聞こえのいい言葉を聞き、世の空気を読むだけでは「真実」が見えないのは、 いつの時代も同じだ。 8月15日<新・人間革命>1979年当時、世界は東西冷戦の暗雲に覆われていた。そしてその雲の下には、大国の圧力に よって封じ込められてじゃいたが、民族、宗教の対立の火種があった。東西の対立は終わらせなければならない。だが、 そのあとに、民族・宗教間の対立が一挙に火を噴き、人類の前途に立ちふさがる、平和への新たな難問となりかねないことを、 山本伸一は憂慮していた。 その解決のためには、民族・宗教・文明間に、国家・政治レベルだけでなく、幾重にも対話の橋を架けることだと、 彼は思った。 8月13日<アイデアを出す瞬発力が武器 ”自分のものさし”信じて風を起こす> (ウェブ小説で若者から人気 作家 岡田伸一さん) 8月13日>真似をする必要はない。自分自身の道を見つけよー哲人ソロー 8月11日「もがき、努力したすべての経験をいわば土壌として、そこからある瞬間、生み出されるものが直観なのだ」 ー羽生善治棋士 8月09日<新・人間革命>仏法は、「随方毘尼」という考え方に立っている。仏法の本義に違わない限り、各地域の文化、風俗、習慣や、時代の風習に 随うべきだというものである。それは、社会、時代の違い、変化に対応することの大切さを示すだけでなく、文化などの差異を、むしろ積極的に尊重していく ことを教えているといえよう。この「随方毘尼」という私座の欠落が、原理主義、教条主義といってよい。自分たちの宗教の教えをはじめ、文化、風俗、習慣 などを、ことごとく「絶対善」であるとし、多様性や変化を受け入れようとしない在り方である。それは、結局、自分たちとことなるものを、一方的に「悪」 と断じて、差別、排斥していくことになる。 8月08日<新・人間革命>文豪トルストイが述べた”人間が宗教なしでは生きられない理由”を弟子のピューリコフは、 6つにまとめた。その一つ「宗教なしでは人間は自分のしていることが善いか悪いかを知ることが決して できないからである。」 8月06日<好奇心が才能を開花させる(柏井正樹さん テニスコーチ 錦石圭選手を指導した)> 人間が才能を開き、成長していくには、好奇心が重要です。コートでは、好奇心を満たす挑戦が日常的に 繰り返されました。圭を育成した秘訣をよく質問されますが、”勝手に育っちゃった”と答えています。 あえて言えば、圭の成長を邪魔しなかったということですかね(笑い)。 8月06日>他人と比較し、ものを考える習慣は致命的ーラッセル 8月04日>個人の変革に力を置くSGIの思想に深く共感ーアメリカ 博士 8月01日(「暮らしの手帖」編集長 花森安治)「難解でもないことを難解にいうのはバカな学者がやることだ。難解なことを わかりやすく表現し、正確につたえる、それが編集者のしごとだ」企画案も、「上からひとを見下すよううな」「説教でもたれようか とする」内容が出ると、叱り飛ばして却下した。 8月01日(新・人間革命)生命の内奥から込み上げてくる人間の感情や欲望は、道徳や規律、また制裁の強化など、制度の改革を もってしても、根本的に抑制することはできない。心の変革こそが、個人の幸福を実現していくうえでも、世界の平和を築いていく うえでも、最重要のテーマとなる。「心の練磨に基礎をおかない限り、知性の開拓が人間を尊貴にすることはできない」とはスイス の大教育者ペスタロッチの箴言である。 7月31日「大空へ羽ばたけ!可能性の翼を広げて 未来本部X教育本部 希望座談会」「安心」を生む第一歩は「聞く」こと I 私ごとで恐縮ですが、実は長女が小学6年の夏から、不登校になったことがあったんです。最初は焦るばかりで娘の”声”に耳を 傾ける心の余裕もありませんでした。「もっと私と向き合って」というメッセージを発していたはずなのに。 K 子どもは自分の思っていることを、うまく言葉にできません。でもその行動には全て”意味”があります。 「問題行動」ではなく「問題提起行動」なんです。 I 私も、池田先生のご指導を学ぶ中で気付いたんです。「変わらなければならないのは娘ではない。自分だ」と。すると祈りも、 「不登校を何とかしたい」から「わが子に使命の人生を歩んでほしい」という祈りへと変わっていきました。そして不登校に なってから5年の夏ーーさまざまな物をため込み、あふれかえった娘の部屋の大掃除を、私と娘の二人でやったんです。2週間かけて。 7月29日>救うべきは「人間の心」「一人の尊厳」に目覚めよ(ペレストロイカの設計者 ロシア ヤコブレフ博士) 「人間は戦争をやめず、犯罪をやめず、自然を破壊し続けています。真に誠実な人間ならば、一番の課題は『人間の心を救う』ことだと、 分かるはずです。今、池田会長が、これを進めておられる」「『国』と『政府』が、『社会』と『人間』の上に立っている。 私たちは、このピラミットを逆転しなくてはなりません」SGI会長が鋭く応じた。「その通りです。その逆転作業に、私どもは挑戦して いるのです。だから古い体制からは、絶え間ない攻撃を受けてきました」 7月29日「長編を読め。世界的な小説を嫁」恩師 7月29日>宇宙の台本にはそれぞれの演ずべき役割がーロラン 7月28日>君の胸からでたものが人の胸を引きつけるーゲーテ 7月25日>真に偉大な事業は目立たぬ所で達成されるーセネカ 7月21日>教師とは子どもの可能性を信じ抜く人(「臨床心理士」「学校心理士」の校長 自閉症、注意欠陥 ・多動性障害(ADHD),小児うつ・・。そうした子どもたちに、限りない慈愛を注ぐ T.Oさん) 「教師とは子どもの心に希望の炎をつける人です。子どもの可能性を信じ抜く人です。人間の心を動かすのは、 人間の心だけなのです」・・今、学校目標を「生き方を深め、すてきな大人に育つ」と決め、学校運営に力を 注いでいる。臨床心理士として授業を参観するのが日課だ。「子どもを救っていけるのは、教師である私自身 !」-その信念で寄り添い続ける。 7月17日>皆に笑顔を届けんでー!(舞台役者 魚谷尚代さん) 勝つと決めて広布に走れば、必ず諸天は動く。役者って、舞台に上がったら”丸裸”になるから、”自分磨き”を サボると、一瞬でお客さんに見抜かれる。だからやっぱ、折伏は大事。自分の弱点に気付かせてくれるんやから。 私も臆病で諦めやすい性格やったけど、かなり折伏で鍛えてもらった。友人の幸せを真っすぐ素直に祈り抜けた 時、相手も素直な心で受け止めてくれる。相手は自分の鏡。舞台も同じやわ。 7月16日>成功とは結果で判断せず努力の総計で計るべきー発明王エジソン 7月14日>地震3ヵ月 熊本の地から <他者思いやる心の芽生えが | ”地域の力”で生きることこそ>日本近代史家 渡辺 京二 「過去から近現代を映す」文明を見直す上で有効なことは、過去という鏡から近現代を映し出してみることです。 過去や歴史は、私たちが現在当たり前だと考えていることがかならずしも当たり前ではない、そんな驚きを 与えてくれます。・・江戸期に来日した欧米人が当時、魅了された日本の豊かさに触れていますが、近代化以前の 日本はどのように映し出されていたのでしょうか。・・現代社会ほど、経済が人々の中心部分を占めたことは なかったように私は感じています。 「謙虚に命を受け止めて」私は思想に生きてきた人間です。その思想のために 親しい友と決別することもありました。しかし、思想なんて大したことではなかった。大事なのは人間。 人間としてどう生きるかということです。地震の前から少しずつ考えてきたことでしたが、今回の地震は、 その思いを一層強くしました。 7月13日>明日を求めて SGI会長の対談録Ⅱ 第24回「平和の文化の母」 エーリス・ボールディング博士 「平和」は、単に「戦争がない」状態をいうのではない。平和とは「文化」である。つまり、民衆一人一人の生き方に 根ざし、家庭や地域といった生活の現場から創造していくものである。お互いの差異を認め合い、相手の主張に耳を 傾けて、絶えず争いを統御(コントロール)していく営みのことである。・・・・ 「私は、『個々の人間の行動から出発して平和の波を起こしていく』というSGIの信念に賛同します。 私はかねてから『共同体を構成する一人一人の成長に全力を傾注していく以外に、平和で健全な地球の 未来は見えてこない』と考えてきたからです」そして、過去にはガンジーやM・L・キングなど、社会を 動かしたカリスマ的指導者がいたが、真に重要なのは「それが社会的な運動であり、民衆の運動であったという こと」「民衆の一人一人が、今後の世界がどうなるかについての、新たな認識と自覚を育んだということ」 だと論じた。